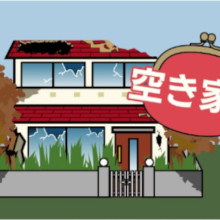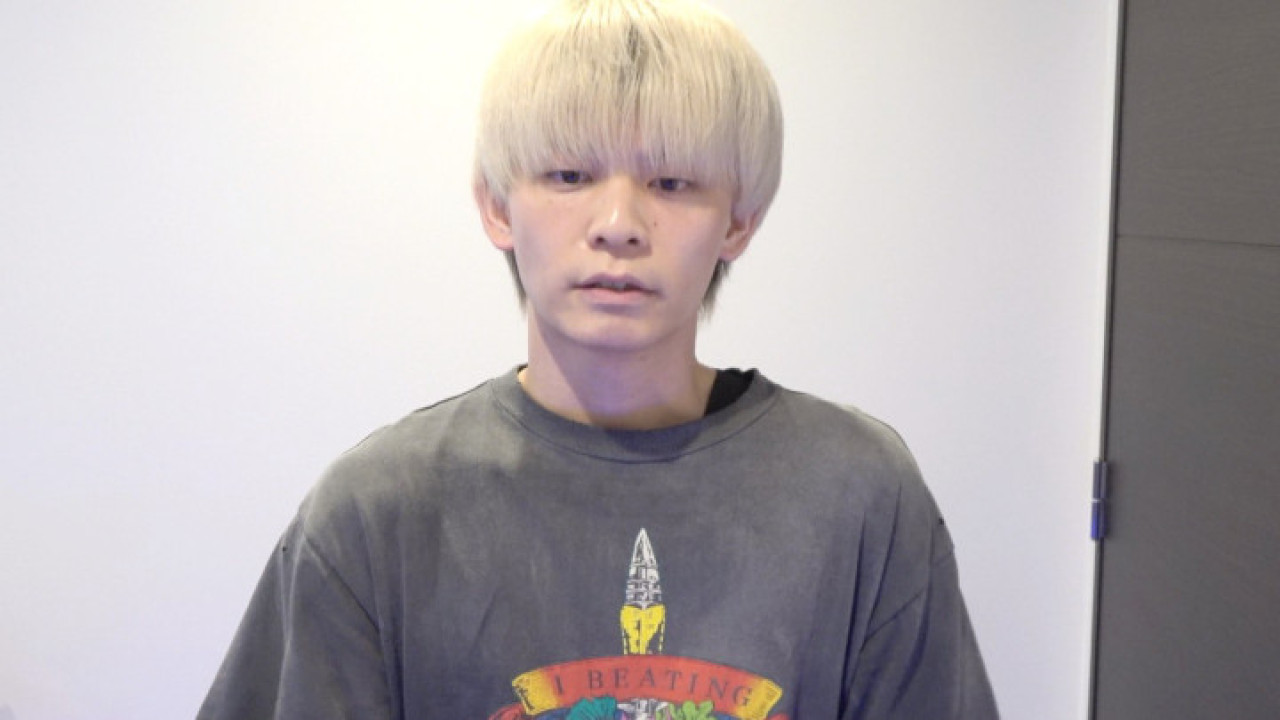日本は1991年のバブル崩壊により、総需要(消費と投資)が不足気味になった。同時に、高齢化により日本政府の社会保障支出が増大する見込みであった。社会保障支出は、もちろん「需要」である。バブル崩壊で総需要が不足気味だった日本国で、高齢化により需要が膨らもうとしていた。
政府はどうするべきだっただろうか。答えは「何もするべきではなかった」だ。
政府が高齢化や社会保障支出を気にせずに、普通に医療費、年金、介護費としての支出を増やしていけば、わが国の需要不足は終わっただろう。もちろん、バブルが崩壊し、名目GDPと税収が減っていたため、財源として赤字国債を発行する必要があるが、逆に言えばただそれだけの話だ。日本政府が「日本円建て」の国債を発行したところで、財政破綻など起こり得ない。長期金利が上昇するというならば、現在の日本がそうしている通り、日銀が市中銀行から国債を買い取れば済む話だ。
ところが、財務省は、
「社会保障の支出が増えるため、他の予算を削減し、増税しなければならない」
という、まさしく「お小遣い帳」の発想で財政破綻をあおり始めた。
90年代後半の日本政府が、大蔵省の「お小遣い帳」発想を排除し、「国の借金で破綻する」系のプロパガンダにだまされず、普通に赤字国債を発行し、高齢化により必要となった医療、年金、介護への支出を増やしていけば、わが国のデフレギャップ(総需要の不足)は埋まった。結果的に、日本はデフレにならず、GDPは今頃、普通に1000兆円を超していたことだろう。
90年代に誰もが予想した通り、その後の日本において、社会保障関係費は増えていった。'15年度に年金や医療、介護などに支払われた社会保障給付費は、高齢化の進展などの影響で、前年度比でおよそ2兆7000億円増加。114兆8000億円強となり、過去最高を更新した。すばらしいことである(注:デフレの国にとっては)。医療、介護への支出は、そのまま「GDP=需要」になる。また、年金受給者が消費を増やせば、これまた需要拡大だ。社会保障関連支出の増加は、日本のデフレギャップ(総需要)を埋める効果があるのだ。
拡大する需要に、政府が淡々と支出をすれば、日本の需要不足は解消され、デフレ脱却に向かう。この状況は、90年代から全く変わっていない。
ところが、現実には大蔵省主導の「財政破綻プロパガンダ」が始まり、日本国は'97年に橋本政権下で消費税が増税された。さらに『財政構造改革の推進に関する特別措置法』(以下、財政構造改革法)を可決。財政構造改革法による具体的な緊縮財政の“強制”は、以下になる。
●財政赤字対GDP比を、毎年3%未満にする(第4条)。
●高齢化に伴う社会保障関係費の増加額をできる限り抑制する(第7条)。
●平成10年度の公共投資関係費について、平成9年度当初予算の93%を上回らないようにする。平成11年度、12年度については、公共投資関係費の額が前年度の当初予算を下回るようにする(第14条)。
●義務教育に対する一般会計の負担および私立学校に対する助成等の在り方について見直し、抑制する(第16条)。
●防衛費の額が、前年度の当初予算を上回らないようにする(第20条)。
●主要食糧関係費の額が、前年度の当初予算を上回らないようにする(第24条)。
●科学技術振興費の額が、平成9年度の当初予算の105%を上回らないようにする(第26条)。
●エネルギー対策費の額が、前年度の当初予算を上回らないようにする(第29条)。
●中小企業対策費の額が、前年度の当初予算を上回らないようにする(第31条)。
●人件費の総額を極力抑制する(第32条)。
●地方への補助金等の額の各省各庁の所管ごとの合算額が、前年度の当初予算の90%を上回らないようにする(第35条)。
などなど、財政構造改革法により、社会保障関係費を除くすべての予算に「マイナスシーリング(予算を前年比で引き下げる)」が掛かるようになってしまった。さらに、社会保障関係費自体も、支出の伸びを抑制することを求められた。
財政構造改革法により、わが国は公共投資、教育費、防衛費、食料安全保障費、科学技術振興費、エネルギー対策費、中小企業対策費、各種人件費、地方の補助金と、国家の基幹に関わる分野でことごとく「予算削減」が続く事態になってしまった。結果、日本は小国化し、発展途上国化している。
ご理解いただけただろうが、財政構造改革法の発想、つまりは「お小遣い帳」の発想を受け継いでいるのが、現在のプライマリーバランス黒字化目標になる。
「'15年度の社会保障給付費114兆円超で過去最高」の報道を受け、日本国民の多くは「お小遣い発想」で、
「このままでは国の財政が破綻する! 増税だ! 政府支出削減だ!」
と、緊縮財政を支持することになるだろう。
結果的に、わが国の少子化と発展途上国化は加速する。国家は外国の軍事力よりも、むしろ国内の情報の誤りにより滅びる。財務省のお小遣い帳発想から脱却しない限り、わが国に未来はない。
「発想」「考え方」とは、これほどまでに恐ろしいものなのだ。ケインズの、
「経済学者や政治哲学者の思想は、それが正しい場合にも間違っている場合にも、一般に考えられているよりもはるかに強力である。事実、世界を支配するものはそれ以外にはないのである。どのような知的影響とも無縁であると自ら信じている実際家たちも、過去のある経済学者の奴隷であるのが普通である(雇用・利子および貨幣の一般理論)」
という文章は、今になっても絶対的な真実なのである。
みつはし たかあき(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、分かりやすい経済評論が人気を集めている。