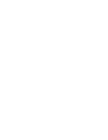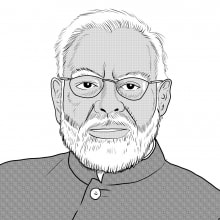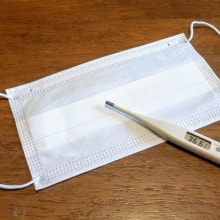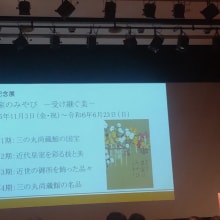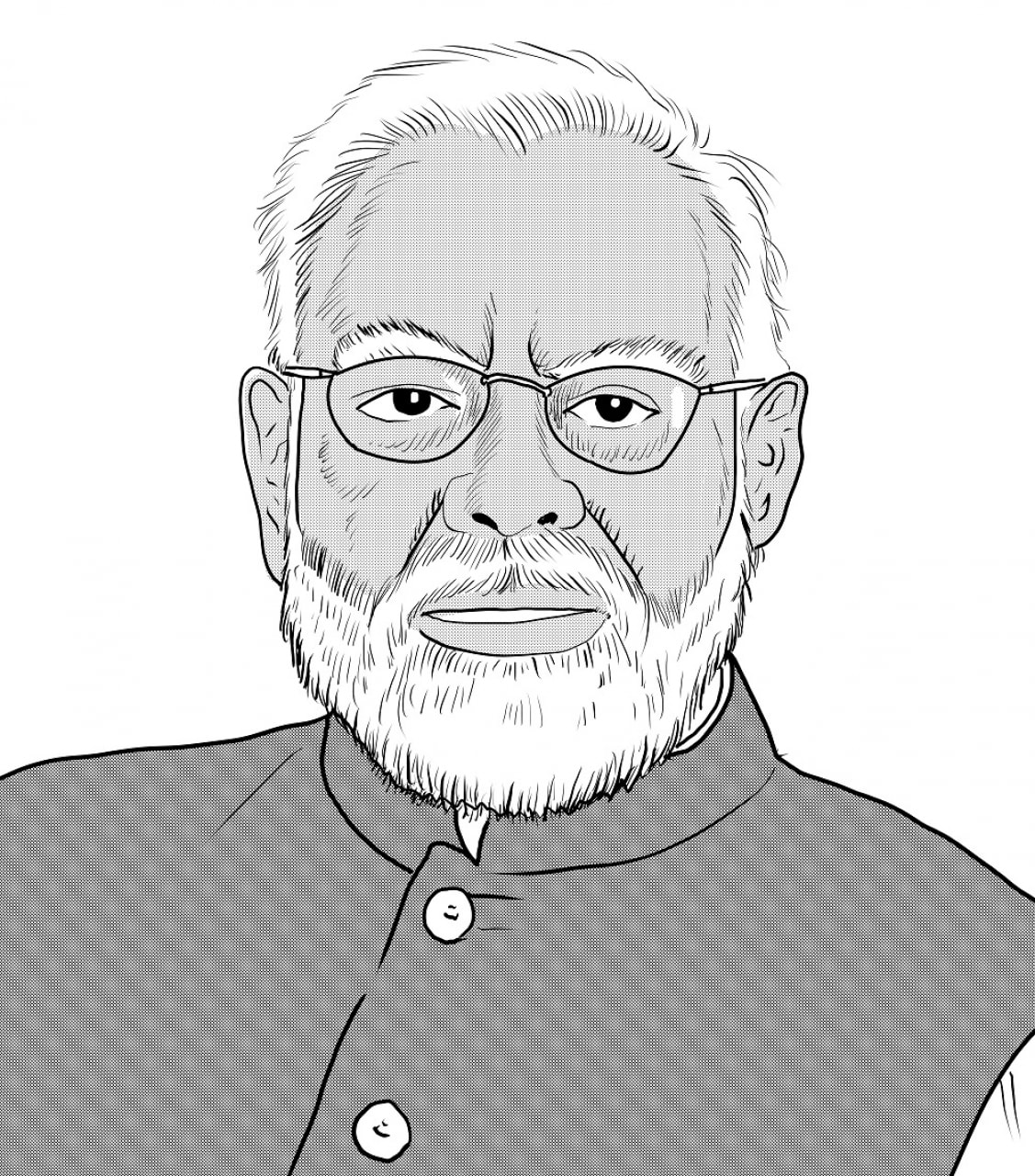「アベノミクスバブルは崩壊した」との評論も目立ったが、そんなことはない。アベノミクスが実質的に始動したのは、野田総理が解散総選挙を決めた昨年11月であり、そのときの日経平均は8600円台で、その時と比べれば、現在でも株価は5割も高くなっているからだ。
ただ、5月23日のピークと比べると、株価が3000円も下落したことは事実だ。その原因は何か。
注目すべきは、為替が円高に向かっているということだ。もしアベノミクスの金融緩和が暴挙で、世界が日本を見放したのであれば、為替は円安方向に暴落していくはずだ。ところが、再び為替が円高になってきているのは、金融緩和が足りないということなのだ。
黒田総裁は、就任早々にマネタリーベースを2年で倍増する計画を発表した。倍増という目標はそれでよいのだが、問題はどのくらいのペースで資金供給を拡大するのかということだ。実は日銀は石橋を叩くようなやり方で徐々に金融緩和を進めている。4月のマネタリーベースの前年比伸び率は23%、そして5月は32%だった。小泉内閣の初期、'02年4月の伸びは36%だったから、いまの資金供給の伸びは、小泉内閣初期の金融緩和にも追いついていないのだ。
経済学では、金利が変わらない場合には為替レートは資金供給量の比で決まることになっている。リーマンショック後、アメリカは資金供給を3倍に増やしたのに、日本がほとんど増やしてこなかった。だから為替は、リーマンショック直前の1ドル110円から、昨年11月の79円まで3割も円高になったのだ。だから、為替を元の110円に戻すためには日本も資金供給をリーマンショック前の3倍に増やす必要がある。
そう考えれば、現在の32%という資金供給の伸び率は明らかに低すぎる。それなのに為替が一時103円まで円安になった理由は、日銀の金融緩和を先取りして為替市場が動いたからだ。そして最近再び円が高くなっているのは、日銀の動きが鈍いことを知った市場参加者たちが、日銀の緩和姿勢を疑い始めたからなのだ。
だから、いま日銀がやらなければならないことは、たった一つだ。いますぐ資金供給の伸びを大きく高めることだ。アメリカはリーマンショック後、資金供給を2倍にするまで、たった4カ月しかかかっていない。日銀の動きは遅すぎる。ところが、日銀は6月11日の金融政策決定会合で、追加の資金供給を見送った。日本経済を再び順調な成長軌道に乗せるチャンスを日銀は放棄してしまったのだ。
あれだけ強気で機動的な金融緩和を主張していた黒田総裁が、なぜ変わってしまったのか。私の目には為替が1ドル=100円を超えた円安に動いたときから、黒田総裁が弱気になったようにみえる。
もしかすると安倍総理とオバマ大統領の間で、金融緩和にともなう円安は、1ドル=100円までという密約が交わされていたのかもしれない。黒田総裁が金融緩和の絶好のチャンスを見送ったことで、日本経済の急激な回復というシナリオは、崩れたとみていいだろう。