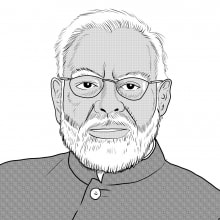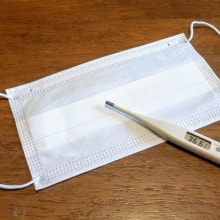経営アナリストが次のように解説する。
「ある市場調査会社によれば、殺虫剤は2020年5月、6月で、それぞれの月間売上高が200億円を突破。対前年同月比で5月は26・1%増、6月は34・9%増の伸びを示した。通常、殺虫剤は夏場のピーク時に月間200億円前後を売り上げるが、今年は早々にその売り上げをクリアしている」
業界最大手のアース製薬(東京)も、中間決算は好調そのものだ。
金融系コンサルタント会社の関係者が明かす。
「8月6日にアース製薬が公表したところによれば、’20年1〜6月期の連結決算は、純利益が前年同期比2.4倍の109億円。売上高も前年同期比6.3%増の1106億円と伸びています」
この好調さは、殺虫剤業界では新規参入組にあたるレック(東京)も同様だ。同社は’18年にライオンから『バルサン』事業を買収して勢いに乗っている。
「’19年に『バルサン』は15億円を売り上げたが、今年2月に投入した新商品群は既存商品の売り上げを上回る勢いを見せている。’20年の売上高目標は40億円を見込んでおり、レックの鼻息は荒い」(同)
では、殺虫剤、虫よけ剤が売れ行き絶好調となった背景は何か。前出の経営アナリストは3つの理由を挙げる。
「まずはやはり、新型コロナウイルスによる巣ごもりの影響があります」
リモートワークの浸透で、夫婦ともに家庭でこなす仕事が増えている。子どもたちの休園や休校措置などに加え、土日の外出も控えめとなり、家庭の生ごみが一気に増えた。
「生ごみにコバエやゴキブリが集まり、発生も活発化。その上、在宅時間が長くなったことで、虫と遭遇する機会が多くなり、退治に奮闘するという流れです。また、窓を開けて換気をする機会が増えたことで、虫が室内に飛来したり、網戸に張り付いたりする頻度が高まりました」(同)
実際、今年は網戸に噴射するタイプの殺虫剤が伸びている。フマキラー(東京)によると『虫よけバリアスプレー アミ戸窓ガラス』が好調で、網戸タイプの売り上げは前年同時期と比べて2.5倍だという。
さて、2つ目の要因としては気象の影響がある。
「ハエや蚊が最も活発化する気温は25℃から30℃です。今年は5〜6月の適度な気温上昇と長雨が、ハエや蚊の増加につながり、それが殺虫剤の売り上げに直結している」(同)
例えば、アース製薬の『液体蚊とり アースノーマット』は、ここ10年ほど売り上げが減っていたが、今年1〜6月は前年同期比20%増、また、同様に『コバエがホイホイ』関連も20%弱伸びている。
3つ目の要素は、業界のグローバル化だという。
「業績面の下支えになっているのが、気温が高く、通年で殺虫剤が使用される東南アジアでの売り上げです。インドネシアに強いフマキラーの海外売上高は、’16年3月期に161億円だったが、’20年3月期には200億円にまで伸び、海外シェアも45%に達している」(同)
しかし、グローバル化で見逃せないのが、海外からの外来害虫だ。
環境省関係者が言う。
「一般家庭の周辺にはまだ襲来していないため、ピンとこない人も多いでしょうが、日本の生態系を破壊する外来害虫がグローバル化の一方で増殖している。例えば、ヒアリやセアカコケグモ(毒グモ)のほか、日本のスズメバチより獰猛でミツバチに甚大な被害をもたらす、ジャワ島原産のツマアカスズメバチなどが脅威となりつつある」
ヒアリは南米原産で、強い毒を持つ特定外来生物だ。刺されるとショック死することもある。
「今年7月、東京港・大井ふ頭のコンテナヤードで約1500匹が確認されたほか、茨城県常総市や横浜港、川崎市内の物流倉庫でも見つかり、日本各地に拡大しつつある。’17年に神戸でヒアリが発見されたときは、フマキラーの株価が急騰しました。同社のアリ用殺虫剤が緊急防除に使用されたためです」(同)
全国各地でヒアリの確認情報が増え、さまざまな外来害虫も増える中、再び殺虫剤が注目されているのだ。
いずれにしても日本の家庭用殺虫剤市場(フマキラー ’20年決算資料での業界市場推定値)は、’16年の1064億円から、’18年は猛暑で928億円、’19年は冷夏で943億円と、ハエや蚊の動きが鈍るのと同時に、業界全体の売り上げも1000億円を割り込んでいた。
しかし、’20年は久々に1000億円市場をにらむ活発な動きとなっている。コロナ禍に加え外来害虫も増殖する中、殺虫剤、虫よけ剤市場の拡大傾向が、今後さらに強まるのは確実だ。