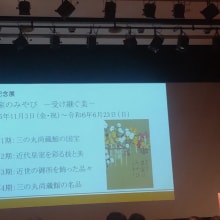「そもそもプロレスのリングが今のサイズになったのは、タッグ形式が生まれた20世紀初頭のアメリカで“タッグ戦にはこのくらいの広さが必要だ”ということで決まったもの。つまり、タッグマッチこそが近代プロレスの神髄とも言えるのです」(プロレス研究家)
しかし、日本においては“最後の決着は一騎打ち”との武士道的価値観が根強く、どうしてもシングル戦より格下のものと見られがちだった。
日本プロレス末期の'70〜'72年に開催されたNWAタッグリーグ戦も不入りの赤字続き。「タッグリーグ戦はダメ」というのがいつしか定説となっていた。そんな風潮を覆したのが、ジャイアント馬場率いる全日本プロレスが旗揚げ5周年記念として開催した、'77年の『世界オープンタッグ選手権』である。
「日プロのリーグ戦の失敗は、馬場と猪木を別チームに分けたことが大きかった。そのため馬場と鶴田の日本勢トップ2がチームを組み、これと対抗できる強豪チームとしてザ・ファンクスらを集めた。その結果“世界で一番強いタッグチームを決める”という文句に偽りのない、豪華メンバーをそろえたのはまさしく偉業といえるでしょう」(スポーツ紙記者)
ブッチャーとシーク、ファンク兄弟はいずれも一枚看板のスター選手。そんなトップどころをセットにするぜいたくさは、この当時、本場アメリカでもなかなか味わえるものではなかった。
さらに馬場の最も大胆かつ革新的な試みとしては、主役に外国人選手を抜擢した点が挙げられよう。シリーズ開幕戦の後楽園ホール、メーンイベントのブッチャー&シークvs馬場&鶴田では、シークによる馬場への急所打ちから、ブッチャーのダイビングエルボードロップでフォール勝ちを収めた後も、最凶悪コンビは執拗に馬場&鶴田をいたぶり続ける。
このとき、救出のためリングに飛び込んだのがテリー・ファンクであった。テリーは最凶悪コンビの返り討ちに合って血だるまにされたものの、日本人を救おうとする外国人の健気な姿は、ファンの心をいっぺんに鷲づかみにした。
「高度なテクニックで評価を得ていたドリーに対し、テリーはNWA王者としての戴冠期間も1年少々と短く、ファンからの印象は薄かった。それが一度の救出劇によって、シリーズの主役になったのです」(同)
公式戦以外でもファンクスとブッチャーらのシングル戦が組まれ、互いの因縁が深まったところで蔵前国技館での最終戦を迎えた。メーンはもちろんファンクスvs最凶悪コンビ。そこまでの星取りでは馬場&鶴田組がトップも、メーンでどちらかが勝てば逆転優勝を果たすことになる。
先に入場したファンクスは、ブッチャー&シークがリングインするや急襲する。試合の主導権を握ったが、ブッチャーの地獄突きから攻守は逆転。そして10分すぎ、シークがテリーの右上腕に凶器攻撃を加えたことから惨劇が始まる。
続いてテリーを襲うブッチャーの右手には、観客の目にもそれと分かるフォークが握られていた。躊躇なくフォークで腕をえぐるブッチャー。おびただしい血がテリーの体を赤く染める。なんとか場外脱出したテリーだが、今度はドリーが捕まってしまう。
エルボースマッシュで凶器ごと吹っ飛ばしても、相手が2人掛かりでは攻勢もそこまで。ブッチャーのエルボードロップをくらい万事休す…。だがそこに、負傷した右腕に包帯を巻いたテリーが復活。最凶悪コンビにサウスポーのパンチを容赦なく叩き込んでいく。国技館は割れんばかりの大歓声に沸いた。
シークがレフェリーのジョー樋口に凶器攻撃を加えたことによる、ファンクスの反則勝ちという結末は、現在の基準なら不透明決着ともなろうが、会場はそれを言わせない圧倒的な多幸感に包まれたのであった。
以後、ファンクスは日本勢を差し置いて全日本の看板スターとなる。そして、この試合が評判を呼び、タッグリーグ戦はプロレス界の冬の風物詩として定着していくことになった。