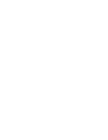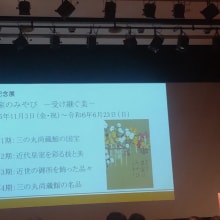ただ、本人の著書などによれば異なる事情もあったようで、あとになって立浪部屋の運営方針にも問題があったとの声も聞かれた。
「例えば『ちゃんこがまずい』と言ったとされる件も、親方が協会から支給されるちゃんこ代を、ケチったことを批判したのだと言われています。北尾自身、転向したプロレス界でも数々の暴言を吐きまくったように、決して人格者というわけではないが、立浪部屋サイドが北尾を悪者にして、責任逃れするために“盛った”部分は少なくないでしょう」(スポーツ紙記者)
人格面だけでなく、幕内優勝の経験がなかったことから、「そもそも横綱にふさわしい実力がなかった」「千代の富士の一人横綱状態を解消するための“仮免横綱”だった」と、言われたりもする。
「パソコンやゲームを愛好し、マイペースな性格もあって“新人類横綱”と呼ばれた北尾は、そのためどこかひ弱な印象もありましたが、実際はそうではない。千代の富士は『もし北尾が廃業していなければ、その後の53連勝、ひいては国民栄誉賞受賞もなかったのではないか』と、当時を振り返っています。実際の対戦成績も、北尾の横綱昇進後は2勝3敗とほぼ互角。幕内通算でも6勝8敗と健闘していて、全盛期の千代の富士を相手に、これだけの成績を残した北尾が弱いはずがありません」(同)
実際、横綱昇進時には、69連勝の大横綱・双葉山襲名の話も出たほどで、結局、立浪部屋の定番である羽黒山と合わせた「双羽黒」の四股名となったが、それほどまでに周囲の期待は高かった。
とりわけ、当時の春日野理事長(元横綱栃錦)は北尾を高く評価して、渋る立浪親方を説得してまで双羽黒の名を薦めたという。
そんな高評価を決定付けたのが、横綱昇進の前年、'86年の5月場所における小錦との取組であった。
'84年に入幕2場所目にして、千代の富士と隆の里の両横綱から金星、大関の若島津からも勝利を挙げ、“黒船襲来”と畏怖されていた小錦。2場所連続で二桁勝利を収め、この場所に大関獲りを懸けていた。
「高校ではアメフト部で主将を務めるなど、巨漢でありながら足腰が強い。入幕当初は巨体頼りの荒っぽい取り口でしたが、徐々に相撲も覚え、外国人初の横綱昇進は確実と目されていました」(同)
今では白鵬をはじめとして外国人横綱も当たり前となったが、しかし、当時は「日本の国技たる大相撲の伝統が崩れる」と、忌避感が強かった。小錦の発言など、ささいなところを批判しては、“横綱にふさわしくない”との評判を立てようとする動きが見られたほどだった。
そんな小錦の前に立ちはだかったのが北尾である。取り直しの一番、軍配が返ると同時に全体重を掛けた突き押しに出る小錦。がっちり受け止めた北尾は、小錦の右腕を左手でつかんでロックアップ。そこからまわしを取って、正面からのがぶり寄り。
これをこらえてつり上げようとする小錦に、鯖折りの体勢となった北尾が、上からのしかかるようにして体を預けると、小錦は右膝から崩れ落ちた。
この一番で小錦は靭帯損傷に骨折という大けがを負い、復帰後は以前と異なり、下半身の脆さを見せるようになった。このときの故障のために、小錦は横綱になれなかったとの声も根強い。
一方、勝った北尾は“黒船を返り討ちにした大相撲界の救世主”との評価を得ることになった。当時、体重240キロの小錦と正面から組み合って、文字通りひねり潰すことなど、たとえ千代の富士でもできる芸当ではない。
横綱昇進後も、毎場所のように優勝候補に挙げられていた北尾。廃業時でもまだ24歳と若かっただけに、あの“事件”がなければ大相撲史に残る横綱となっていたかもしれない。