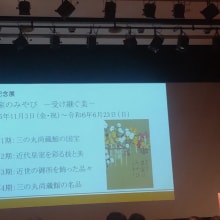競技人口の多い柔道界においても、これだけの体格を誇る選手はそうそう見当たらず、そんな坂口がなぜプロレス入りしたのかといえば、これはもう時代の巡り合わせとしか言いようがない。
1964年の東京五輪で初の正式種目となった柔道だが、日本勢は重量級でアントン・ヘーシンクに完敗。そこから決死の巻き返しを図るも、次のメキシコシティ五輪では競技自体が実施されなかった。日本柔道界の将来には暗雲が垂れ込め、それはまた坂口にとっても同じだった。
そんなとき、日本プロレスからの誘いがかかる。スカウトの席で分厚いステーキが振る舞われ、「こんないいものが食えるのか」と心揺らいだとの逸話からも、当時の坂口および日本柔道界の不遇の様子がうかがわれる。
しかし、坂口は同時に弱点も抱えていた。柔道時代に痛めた腰の不安である。
「ブリッジなどの練習は、ほとんどしなかったと聞きます。身体を反るスープレックス系の技もまず使わない」(古参プロレス記者)
たまに繰り出したブレーンバスターも相手を後ろに投げ放つのではなく、頭上に抱え上げたところで自ら尻もちをつくように落とすもので、まさしく和名通りの“脳天砕き”。あまりにも危険だからと、いつしか封印されてしまった。
「相手にボストンクラブをかけられそうになれば、やはり腰の不安から慌てて跳ねのける。互いに使える技が限られてしまうから、どうしても試合が単調になりがちでした」(同・記者)
アメリカでUN王座を獲得した試合('72年、対キング・クロー)でも、「アトミック・ドロップ6連発でフォール」と、いかにも大味なものであった。
坂口のそんな“粗さ”も、相手次第では“荒々しさ”となってプラスに転じた。坂口自身も名勝負として挙げるドリー・ファンク・ジュニアとのNWA王座戦('71年)は、ドリーのテクニックと坂口のパワーが実にうまくかみ合った試合となった。
坂口は柔道で寝技の基礎ができているからグラウンドでの攻防もスムーズで、そこが他の単純なパワーファイターとは異なる点だ。両者はよほど手が合ったようで、坂口の修行時代のアメリカでも、ドリーとは60分フルタイムの試合を行っている。
また因縁、遺恨のある相手との対決というのも、坂口の本領が発揮される舞台となる。
日プロ末期の因縁を引きずる大木金太郎戦−−。
互いに“裏切り者”と憎み合うリング上に、多彩な技など必要ない。大木の原爆頭突きに坂口が力任せのラフ殺法で立ち向かい、新日での都合3度の対決は、いずれも無効試合などの不透明決着。それでも、2人の感情ほとばしる試合は今も伝説として語り継がれている。
イデオロギー対決となった新日対UWFの5対5勝ち抜き戦−−。
次鋒として登場した坂口は、当時としては格下だった高田伸彦(現・延彦)、山崎一夫を次々と蹴散らし、「坂口強し!」をあらためて印象付けた。そんな坂口の姿に新日ファンは快哉を叫んだものだった。
「おやじは強かった。でも優しすぎた」
坂口の息子で俳優の坂口憲二が、テレビの企画でカール・ゴッチを訪れた際に掛けられた言葉である。
坂口が、そんな優しさのリミッターをリング上で常に外すことができれば、もしかすると猪木以上のスターとなったのかもしれない。
「それでも、サカさんが常に猪木さんより一歩引いて事務方に専念してくれたからこそ、新日本は幾度ものピンチにもつぶれずに存続することができた。その意味では、新日本の一番の恩人なんです」(元・新日関係者)。
〈坂口征二〉
1942年、福岡県久留米市出身。'65年、全日本柔道選手権優勝。'67年、日本プロレス入団。'72年、新日本プロレスへ移籍し、猪木に次ぐスター選手に。'90年、社長業に専念するため引退。次男は俳優の坂口憲二。