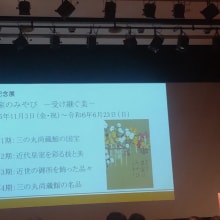柔道との出会いは10代も後半と遅かったが、生まれ持った強靭な肉体と人並み外れたパワーをもって一足飛びに頂点にまで上り詰めた。
「俺を差し置いて格闘技世界一などとは、しゃらくさい」と猪木アリ戦に割り込んだルスカ。そんな勇ましい宣言にふさわしいだけの実力と実績があったことに疑いの余地はない。
だが、その試合の契約書には「猪木に勝ってはならない」との条項があった。決して「格闘技最強」を目指したわけではなく、ファイトマネー目当ての参戦だったのだ。
ルスカと同じオランダ出身の柔道金メダリストに、東京五輪無差別級のアントン・ヘーシンクがいる。そのヘーシンクが国民的英雄として讃えられた一方で、ルスカが生活に困窮するまでに至った理由の一つには所属団体の違いがあった。主流派のへーシンクに対し非主流派のルスカは競技引退後、酒場の用心棒に身をやつしたりもしたという。
では、そうした経緯で行われた猪木とルスカの“プロレス”が“真剣勝負”ではないから価値がないのかといえば、決してそうではない。むしろ猪木の数多くの試合の中でも上位に挙げられる名勝負といえよう。
1976年2月6日、日本武道館。後に続く異種格闘技戦の第1戦−−。試合開始早々からルスカは払い腰で何度も猪木をリングに叩きつけ、裸締めや袈裟固め、腕十字で攻め立てる。対する猪木も柔道にはないエルボーやナックルパートの打撃技で逆襲すると、リング中央、コブラツイストで締め上げてみせる。
一進一退の攻防の続く中、倒れたルスカの頭部に容赦なく蹴りを放った猪木。これに対して怒ったルスカが柔道着を脱ぎ捨てると、その北欧人独特の白肌は真紅に染まっていた。
この試合前、ルスカは同門のサンボ王者クリス・ドールマンを伴って新日本プロレスの道場に出向き、猪木と手合わせをしたという。
「猪木の真剣勝負はアリ戦とパキスタンでのアクラム・ペールワン戦、韓国でのパク・ソンナン戦の計3戦だけ」などとまことしやかにいわれるが、その一方で「結果は決まっていても試合自体はナチュラルだった」との関係者の証言も多い。試合展開の筋書きを完全に作り上げることは猪木自身が好まなかったし、弟子たちにもやらせなかったというのだ。
そんな猪木が予行演習までしたというのだから、それほどにこのルスカ戦は、アリ戦に向けて決して失敗することのできない試合であり、猪木からしてみればこれこそが“真剣勝負”だったともいえるだろう。
そして、そんな猪木の意気込みは見事に成就する。バックドロップ3連発でルスカをTKOに下すまでは見せ場の連続。20分35秒というプロレスとしてはいささか長めの試合中、観客はひとときも飽きることなく歓声を送り続けることになった。
“結果が決められていない”という意味での真剣勝負、アリ戦と比べてみたときに、どちらの価値が高いかとなると意見も分かれようが、試合中の観客の熱狂度合でいえば明らかにルスカ戦が上回っていた。
大目標であるアリ戦の前に突如現れた大物刺客・ルスカ。これを見事討ち果たし大舞台へのステップを一段上がった猪木。
そんなストーリーラインから試合内容まで、全てが完璧にそろったという点で、やはり猪木vsルスカは日本格闘興行史でも屈指の名勝負といえよう。
激闘の末にバックドロップに沈んだルスカを見て、リングにタオルを投入したのはセコンドに就いたドールマンであった。そのドールマンは後に「オランダ格闘技界のドン」と称され、前田日明のRINGSを盛り立てるなど格闘史にページを刻むことになる。
アントニオ猪木とウィレム・ルスカ。それぞれの格闘遺伝子は、今なお脈々と受け継がれている。