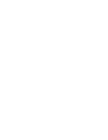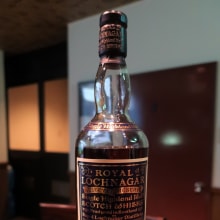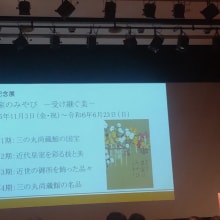尿酸の蓄積は健康診断でも示されるが、「日本痛風・核酸代謝学会」のガイドラインでは、1デシリットル当たりの血清尿酸値が7ミリグラムを超えると、年齢・性別を問わず「高尿酸血症」と定義、つまり、痛風予備軍の仲間入りをするとしている。
しかし、「尿酸値が“7”を超えると尿酸が結晶化しやすい」としながらも、
「数値の“7”はあくまで一つの目安。臨床の現場では、7未満でも痛風発作を起こす人がいるし、その逆もあります。ですから“7以上は危険、7未満は安全”と単純に考えるのは改めるべきです」と語るのは同学会関係者だ。
また、東京多摩総合医療センター内科担当医も、痛風の発作と尿酸値の関係についてこう説明する。
「よく言われますが、尿酸値さえ下げれば痛風は起こらない、という考えは間違いです。複数の調査で、尿酸値が高い人は、もともと末期腎不全などの腎機能障害や心血管障害のリスクの高いことがわかっています。こうした患者は、痛風患者と違って命に関わる病気ですので、治療も最終目的である人工透析が必要です。しかし、尿酸値が高いから“腎機能障害や心血管障害が起きる”。あるいは“腎機能障害が起きているから尿酸値が高い”“腎機能障害のせいで心血管障害を起こしやすい”については、まだはっきりとわからないところがあります。ただ言えるのは、こうした機能障害を防ぐには、生活習慣を見直し、尿酸の“低値”を目標にすべきでしょうね」
言い換えれば、痛風には未解明の部分があるものの、尿酸値が高いと言われたからといって、直ちに痛風に結びつけるのではなく、心血管障害などのリスクを負っていることも念頭に置くべきいうことだ。
厚生労働省の国民生活基礎調査(2010年)では、痛風で通院している患者は全国で約95万7000人。'86年の25万4000人と比べて4倍近く増加していることがわかる。そのうち男性が約9割を占め、発症は30代が最多で、20代もまれではない。生活習慣病を予防する健康管理士・長剛正さんは言う。
「痛風という病気が若年化傾向にあるのは、現代のような飽食の時代に突き進んだことも関係しています。痛風の発症には、遺伝的な体質と食生活などの環境要因が絡んでいると思います。食事で注意すべきは、プリン体の摂り過ぎ。プリン体は体内で分解されると尿酸に変わる物質で、動物の内臓や魚の干し物、しらこなどに多く含まれる。もちろん、ビールもプリン体を含み、痛風の原因といわれますが、アルコールのすべてが体内で尿酸を大量に作り、尿酸の排泄を妨げます。ビールに限らず、飲み過ぎは避けることですね」
ビールが痛風云々と騒がれるのも、ビールに含まれるプリン体が体内への吸収率が高いためだが、飲み過ぎると尿酸値が上がる。それを誇大に「ビール=痛風」になっているようだ。
「太る。メタボだ!」も、ビールじゃなくおつまみが問題。せいぜい、「豆腐、枝豆、鳥のささみ、おひたし」辺りにとどめておけば、ビールは美味しく、安心してグイ〜ッといける。