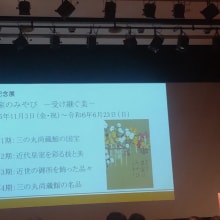K-1を「茶番」と言い放ち、自身のキック道にまい進する姿は、昔ながらのキック愛好家たちの共感を呼んだ。
中学卒業と同時にタイへ渡り、本場ムエタイの修業を積んだ立嶋。衰退の一途だったキック界に、こんな若者がいることがファンからすれば奇跡であり、16歳で日本デビューを果たすと早々から大きな期待をかけられた。閑古鳥の鳴いていた後楽園ホールは、それこそ立嶋の試合となると満員の観衆が詰めかけるようになっていった。
「キックボクシングとK-1の一番の違いは“ヒジ”の有無です。ルール上、ヒジでの加撃が認められているキックでは、これを当てるためにどうしても相手との間合いが近くなり、常にインファイトの状態で激しいドツキ合いになるのです」(格闘技ライター)
ヒジでの打撃はグローブでのパンチとは比べ物にならないほどの破壊力で、当然KO決着は多くなる。また、ヒジを鋭角に当てることでまぶたや目尻の皮膚は簡単に裂け、出血でのTKOも珍しくない。
このためリング上で戦う選手たちはもちろんのこと、観客もまた一瞬たりとも気が抜けない。
K-1が“ヘビー級の一撃必殺”を売りにしたのとは対照的に、軽量級の息をも付かせぬスピーディーで激しいファイトがキックボクシングの持ち味で、ヒジの有無によってまるで別競技の趣となる。
「そんな中でも立嶋は特にヒジを得意としていて、その試合ぶりはまさに“殺るか殺られるか”です」(同・ライター)
立嶋本人も「客がキックの試合に来るのは、残酷なものを見たいから」と語っている。その言葉の通り、常に観客の目を意識して試合に臨んだこともあって、'92年に清水隆広戦で勝利して全日本フェザー級王者となるまでの戦績は23戦14勝7敗2分け(タイでのデビュー戦を含む)と、勝率そのものは決して高くはなかった。キックファンは立嶋の強さというよりも、その人間そのものを愛していたのだ。
そんな立嶋の名前がキック界を超えて広く格闘技ファンに知れ渡ることになったのは、'93年11月の前田憲作戦であろう。
前年、前田のテクニックの前に判定で敗れた立嶋。その後にはムエタイランカーに一方的に攻められてのKO負けなどもあり、決してリベンジマッチまでの道程は順調ではなかった。
片や前田はというと、欠場選手の代役として臨みながらの王座戴冠で、それにより一足飛びに全国区のファイターとして認知されるようになっていた。
焼けた肌に笑うと白い歯がまぶしい前田と、青白い情念に包まれたかのごとき立嶋では、そのルックスからしても好対照。格闘技専門誌などは両者のライバル関係を喧伝し、また2人もこれに呼応した。
試合前、立嶋がいつも披露する居合い斬りを模したワイクー(ムエタイの儀式)に先んじて、上段斬りの構えを見せる前田。立嶋もこれを受けて下段に構える。互いに虚空を斬り合って始まった試合は、その結末もまさに真剣の切れ味だった。
クビ相撲からの立嶋のヒザが前田の顔面を捉え、前田の頭が浮き上がると、その瞬間に立嶋はヒジを一閃、打ち下ろす。うつ伏せに倒れた前田は何とか腕で上半身を起こして立嶋を見上げたものの、立ち上がることはできなかった。
3R0分49秒−−。
立嶋は王座奪還を果たすとともに、ライバル物語に痛烈なピリオドを打ってみせたのだった。
この試合後、立嶋は海外大物選手を立て続けに下し、キック界の一枚看板として君臨することになる。一方の前田はK-1に転身。2002年には引退し、指導者となった。
後進のキック界のスター候補たちは続々とK-1へ転向していったが、しかし立嶋はキック界の孤塁を守り、40歳を過ぎた今もなお現役にこだわり続けている。長男の名前は「挑己」(いどむ)。今年1月、父と同じ16歳でキックのプロデビューを果たした。