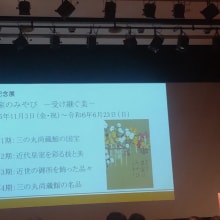死因はバックドロップを受けた衝撃による頸髄離断。技を掛けた齋藤が特に危険な落とし方をしたわけではなく、また三沢も受け身を取り損なった様子はない。つまりは、マットに“正常に”落ちた際の衝撃による不測の事故であった。
原因として第一に言われたのは、長年のレスラー生活におけるダメージの蓄積だ。晩年の三沢は慢性的な首、腰、ヒザ等の痛みに苦しみ、日常生活にも支障を来すほどであったという。
「モノマネの神奈月がよく武藤敬司のヒザの悪さをネタにしていますが、三沢の場合、全身がそんな状態だったと思えばわかりやすいでしょうか」(プロレスライター)
NOAHを旗揚げした後には社長業にも時間を割かれたためか、コンディションの悪さは傍目にも歴然で、これも事故原因の一つとなった。
「何しろ一気に太りましたからね。きっとトレーニングの時間もまともに取れなかったのでしょう。社長室で通販のダイエット器具みたいなものを見たこともあります」(同・ライター)
それでも三沢は休むことをしなかった。対戦カードに三沢の名前があるとないでは興行の客入りからして違ってくるため、団体運営のためにも出場せざるを得なかったのだ。
やはり、全日本プロレス〜NOAHのために命を削った末の“戦死”であった、と言える。三沢の死に接した関係者やファンからは、全日本時代からの過剰な試合ぶりに対する批判的な声も聞かれた。“相手をアタマから落とす危険な技の連発が肉体を蝕んだ”と。
だが、それも三沢自身の選んだ道である。
天龍源一郎が退団、ジャンボ鶴田も内臓疾患により一線から退く中、エースの座を担う三沢は“鶴龍”を超える闘いを見せる必要があった。当時のジャイアント馬場社長からは“マイクアピールやギミックに頼らない、流血や反則もない、ピンフォール決着を”との要望もあり、そうして行き着いたのが、いわゆる『四天王プロレス』だった。
三沢、川田利明、田上明、小橋建太の4人をはじめとし、次世代の秋山準、外国勢では殺人バックドロップのスティーブ・ウィリアムスらも加わり繰り広げられた、世界中のプロレスシーンにも類を見ない激しい闘い模様−−。試合序盤からハードヒットの打撃と急角度の投げ技を互いに出し合い、カウント2.9の応酬で、終盤にはエプロンサイドから場外床に向けてパワーボムなどを放つこともしばしば。グラウンドの攻防などレスリング要素を欠く内容から「ただのタフマンコンテスト」と批判的に見る向きもあったが、出し惜しみも不完全決着もない好勝負保証付きの試合ぶりはファンからの熱烈な支持を得て、ビッグマッチは常に満員御礼。馬場、鶴田の影を払しょくしたのみならず、三沢は日本プロレス界のエースとして認知されることにもなった。
そんな四天王プロレスの最高峰といえば、馬場も解説席で涙を流した(副音声の実況アナとゲストの川合俊一氏が「馬場さんが泣いています」と叫んだ)1998年10月31日、日本武道館。三冠王者の小橋に三沢が挑戦した一戦が挙げられよう。
三沢自身、川田らとの試合との比較の中で「小橋戦こそ極限の力を見せられる」と語っていた、まさにその言葉通りの究極マッチとなった。
この試合でも序盤に頭から投げ落とすスープレックスを出し合い、中盤過ぎにはもう立っているのもやっとの状態に。そうなってなお、ギロチンドロップを放つ際の前動作にサマーソルトを加えるあたりが、常に華麗さを求めた三沢プロレスの真骨頂だ。
フィニッシュは派手な投げ技ではなく左右エルボーの連打で、43分29秒、精根尽き果ててマットに崩れた小橋を三沢が押さえ込んだ。
この一戦を含め三沢と小橋のシングル対決は、3度にわたりプロレス大賞(東京スポーツ新聞社制定)の年間最高試合賞を受賞している。
後にも先にも比類なき、日本プロレス史に残る文化遺産なのである。