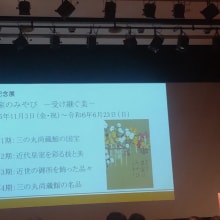さまざまなレスラーのニックネームの中にあって、フレアーのそれほど似つかわしくないものはないだろう。日本のリングでは、一切“狂乱”の素振りなど見せることがなかったのだから…。
「NWA王者となってからのフレアーは、狂乱とは真逆の“職人芸”を披露し続けたレスラーですからね」(プロレスライター)
何しろ“デクの坊”との誹りさえあった輪島でさえも挑戦者に迎え、NWA王座戦を成立させているのだ。そのプロレス・スキルの高さたるや、およそ余人のかなうところではない。
「他にも全日本プロレスでは、谷津嘉章やザ・グレートカブキ、タイガーマスクらとも防衛戦を行っています。とてもタイトル奪取の望めないような面々を相手にして、きちんと見せ場を作り観客を納得させる。挑戦者を実力以上に持ち上げた上で最後はちゃんとタイトルも防衛するのだから、これはもう立派なものです。ただ、長州力のような直線的な選手が相手のときに限っては、フレアーの試合運びのうまさばかりが目立ってしまうのですが」(同ライター)
AWA王者リック・マーテルや、IWGP王者藤波辰爾とのダブルタイトルマッチというような、勝敗や展開にシビアなサジ加減が要求される試合が度々組まれたのも、フレアーの“職人技”に対するプロモーターからの信頼があってこそだろう。「絶対に試合を壊さない」という安心感があるから、双方の看板タイトルをかけることもできたのだ。
バックハンドチョップでリズムを作り、脚攻めからの4の字固めというのが定番ムーブ。使う技は限られたものだったが、しかしフレアーの真骨頂は“攻め”よりも“受け”にあった。
デッドリードライブで派手に投げ飛ばされ、コーナーに追い込まれれば「ノー、ノー」と両手を差し出す。大技をくらえば顔面からマットに倒れこみ、コーナーに振られれば身体を一回転させて場外に転げ落ちる…。
惜しむらくはフレアーが王者として君臨していた当時、日本のプロレスファンは“強さ”を求めていたことだ。「フレアーの試合展開は好きじゃない」と語った天龍源一郎に代表される“激しいプロレス”が多くの支持を集めていた。
ジャイアント馬場がNWA王座就任前の試合ぶりから「いずれ天下を取る」と見初めたように、また武藤敬司が「自身のプロレスのベース」とあがめたように、フレアーを高く評価する声も多かったが、しかしそれが直接の人気にはつながらなかった。
フレアーはあくまでもNWA王座戦という“お祭り”における“神輿”にすぎず、伝統あるベルトへの敬意は抱いても、フレアー個人は認めないというのが多くのファンの姿勢だった。
日本のファンのそんなフレアーに対する意識が大きく変わったのが、1995年に行われた『北朝鮮平和の祭典』でのアントニオ猪木戦だった。
既に全盛期を過ぎた老境の猪木を相手にしながら、19万人の大観衆を盛り上げたのは、紛れもなくフレアーのスキルの賜物である。
「今になって、あの試合での大声援を《朝鮮労働党が観客を指導して演出したもの》という声もありますが、トンデモない。その前日までは、盛り上がったのは女子の試合だけ。メーンの橋本真也対スコット・ノートンでも客席が静まり返っていたから、選手たちはみんな焦りまくっていたんです。それが一転してあの大歓声でしょう。あれはフレアーと猪木という2人のスーパースターが呼び起こしたものです」(当時、現地で取材した記者)
ショーマンプロレスを批判してきた猪木が、その権化であるフレアーと好勝負を演じたことにもファンは驚かされたものだった。
「ブッキングは、当時新日本プロレスと提携していたWCWエリック・ビショフの推薦によるものでしたが、それをすんなり受けたのだから、猪木さんもフレアーのことを認めていたのでしょう。世界から注目される大一番で、評価しない相手と戦うはずがありませんから」(当時の新日関係者)
ショーマンスタイルも究極に達すれば、ストロングスタイルからも認められる存在となるのだ。
〈リック・フレアー〉
1949年、アメリカ出身。'73年、国際プロに初来日。以後は全日プロを主に、NWA王者として数多くのタイトル防衛戦を行う。WCW時代には新日プロにも参戦。アントニオ猪木との北朝鮮での歴史的一戦にも臨んだ。