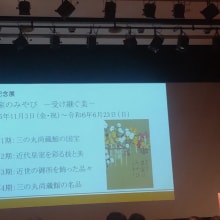「優秀なアマチュア」と言ったのは、一時期バックランドをコーチしたこともあるカール・ゴッチだ。
「欧州式のシュートな関節技こそが至高であり、それを身に付けてこそ本物のプロ」というゴッチの思想からすれば、全米大学王者の経歴を持つバックランドのレスリングテクニックがいくら優れていようとも「それはアマチュアの域を出るものではない」ということなのだろう。
「ストロングスタイルのなんたるかを理解していない」と酷評したのはアントニオ猪木。大技を繰り出した直後、相手に合わせるようにリング上で伸びているバックランドに対しての言葉である。ただ、これは後の四天王プロレスでもよく見られた光景だし、観客に大技の余韻を伝える効果もあるわけだから、単に好みの問題とも言えそうだ。
それらよりももっと否定的なのは「実力はあるが客は呼べない」というキラー・カーンの言葉であろう。一時はマディソン・スクエア・ガーデンの同じリングに上がっていたカーンの言葉だけに真実味は高い。
見るからに優等生風の外見で、お決まりの攻めを繰り返すバックランドの試合スタイルは、なるほど刺激に薄く、観客からの人気は決して高くなかった。“悪のオーナー”ビンス・マクマホンに、そのアスリート色の強いスタイルが「新時代のプロレス」と気に入られて王者となったまでは良かったが、実際に観客からの人気を集めたのは大巨人アンドレ・ザ・ジャイアントであり、WWFの全米侵攻に際してはニュースターのハルク・ホーガンにその王座を(アイアン・シーク経由で)譲らされることにもなった。
また、そうした扱いはアメリカだけのことではなく日本でも同様で、バックランドのプロレスラーとしてのパフォーマンスは横に置かれ、世界王座保持者という肩書きだけを重宝するカード編成がまま見られた。
新日時代でいえば、1982年の元日に行われた藤波辰爾との試合などはその最たるものと言えよう。世界タイトル戦にもかかわらず、メーンは猪木vsローラン・ボックに譲ってのセミファイナル。しかもその決着は、藤波が後方回転エビ固めを仕掛けている最中にマットに肩がついていたとしてレフェリーが3カウントを入れるという、実に不透明なものとなった。
藤波にとってヘビー級転向直後の『飛龍十番勝負・第1戦』という大事な試合であったとはいえ、時の世界王者にまともなピンフォール勝ちを与えないというブックは、いかに新日がバックランドを軽視していたかの表れだろう。
「でもU系に出場するようになってからは、もっと悲惨でしたよ。船木優治(現・誠勝)にミサイルキックを食らってなぜか反則勝ちの裁定を受けたり、Uインターでの高田延彦戦では金的への蹴りで秒殺されたり…」(プロレス誌記者)
いずれもバックランドのかつての名声を利用して日本人選手の格上げを図り、なおかつ不透明決着とすることでバックランド自身の商品価値は落とさずに使い続けようという、フロント側の意図が透けて見えるようではないか。
U系に参戦していたころは時代状況も悪かった。
「UWFではゴッチ直伝の関節技こそが最上の価値とされ、また見栄えの良さから打撃が重視されていました。そんなふうだからバックランドの本来持ち合わせたレスリングテクニックは評価の対象外。地味な中堅選手にすぎなかったころの安生洋二にすら、打撃で圧倒されるような試合をさせられていましたからね。だけど、後に総合格闘技でタックルなどが最重要視されるようになったことから考えれば、本来“何でもあり”ならバックランドは相当に強かったハズです。少なくともUWF勢に不覚を取るレベルではなかったでしょう」(同・記者)
持ち前のレスリングテクニックを存分に生かすことなく、力任せのパワーファイターとしての闘いを余儀なくされたバックランド。四半世紀生まれるのが遅ければ、プロレスと総合格闘技を股にかける真の王者として君臨していたのかもしれない。
〈ボブ・バックランド〉
1949年、アメリカ出身。大学のレスリング選手権で優勝した後、'73年プロデビュー。翌年、全日プロに初来日。'79年以降はWWF王者として新日プロに参戦。'90年代初頭にはUインター、WARなどのリングにも上がった。