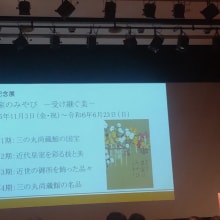ところが、バンドー空手の使い手という触れ込みのラジャは(ちなみにバンドーとはミャンマーの武術で、素手のキックボクシング的なもの)、試合前の公開練習でキックを放つと同時にすっ転んだことで、早々に“ズブの素人”であることが露見してしまう。
「実は新橋のカレー屋店員をスカウトしてきた」との噂がまことしやかに語られるほどで、つゆほどの緊張感も見られないまま試合当日を迎えることになった。
それにしてもなぜ、馬場の生涯唯一となる異種格闘技戦が、このような形で行われるに至ったのか。
まず、「猪木の異種格闘技路線に対抗して」というのは、猪木自身が格闘技戦を最後に行ったのがこの3年前で、それにわざわざ対抗する必然性がない。
また、「UWF人気にあやかって」という説も説得力に欠ける。この頃、新日vsUWFの対抗戦は確かに人気ではあったが、それはあくまでもコアなファンの間でのこと。決して広く支持されていたわけではなく、テレビ中継の視聴率も低迷していた。よって、これも“プロレスの王道”を自負する馬場が真似するようなものではない。
「理由は当時の馬場と全日が置かれた状況にありました」(プロレスライター)
'85年にPWF王座をスタン・ハンセンに奪われてからは、第一線から退いた状態にあった馬場。ハンセンらが馬場を厳しく攻め立てると、観客から「手加減しろ!」とのヤジが飛ぶようなありさまだった。
しかし、ラッシャー木村との義兄弟タッグ、ファミリー軍団の結成はまだ後々のことで、よく言えば馬場は“一人レジェンド枠”であり、実際のところは現役選手として、中途半端な立ち位置にあった。
だが、そんな馬場を、形ばかりとはいえ異種格闘技戦なる大一番に駆り立てざるを得ない事情が、このときの全日にはあったのだ。その原因とは、長州の新日電撃復帰である。
「興行の目玉の一つだった長州の欠場により、武道館大会はカード編成からして困難な状況でした。長州をアテにしていたため参戦外国人選手の数も少なく、このときの『スーパーパワーシリーズ』のメーンイベンター級は、ロード・ウォリアーズとタイガー・ジェット・シンぐらい。ウォリアーズも初来日時ほどの新鮮味は薄く、ほかにどうしても目玉が必要だったのです」(同)
また、テレビ放送の事情もあった。この頃の全日は土曜19時からのゴールデン中継。だが、同枠での放映となったのも、もともとは長州ら維新軍の人気を当て込んでのことであり、長州離脱により代替の話題性あるカードを求められていた。
そんなこんなで話題性のあるカードを求められ、急きょの間に合わせとして浮かび上がったのが、馬場vsラジャの異種格闘技戦だったのだ。
「一流の相手を呼ぶには時間がなく、また、往時の力がない馬場に好試合も期待できない。だったら話題性を最優先しようというわけです」(元全日関係)
そして、実際の試合も案の定というべき内容だった。
開始早々から左右のキックを繰り出したラジャは、自らバランスを崩してひっくり返る体たらくで、場内の至るところから冷笑が漏れる。チョップやハイキックもスピードや力感に乏しく、ことごとく馬場に防ぎ返されて、第2ラウンドに入ると早々に、馬場がラジャの腕を十字に極めて試合終了となった。
「凡戦とはいえそれでゴールデン中継が成立し、武道館に客を呼べたのだからマッチメーク的には成功ともいえる。素人のラジャだからギャラも格安で済んだようです」(同)
それでも全日は、これに味を占めての珍アングル乱発とはならず、王道プロレスに踏み止まった。
暗黒面に堕ちる寸前の全日を救ったのは、この試合のわずか3日前に結成された天龍源一郎と阿修羅原による“激しいプロレス”であった。