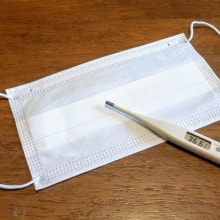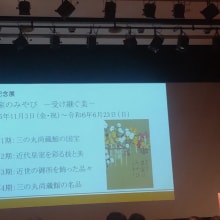当初は「直角内閣」「田中曽根内閣」などと揶揄され、田中角栄の影響下にある政権とみられていたが、田中が“名代”として内閣に送り込んだ後藤田正晴官房長官と歩調を合わせ、官邸主導で次々と大仕事に取り組んだ。現在の安倍晋三政権も「官邸主導」とされているが、同じ政治手法でも中曽根のそれには透明性があった。
高潔、知謀、そのキレ味から「カミソリ」との異名もある後藤田の存在が、内閣はもとより自民党への抑えとなり、政策はオープン、スキャンダルなど不祥事の露呈も、ほとんどなかったのである。
例えば、時のタカ派文部大臣が自らの歴史認識を発言して物議をかもすと、中曽根はこれを更迭、ボヤが政権の大火事となるのを消し止めるといった具合である。この一件も後藤田の「危機管理術」を、中曽根がのんだうえでの更迭だったことは明らかだった。
そうした中で政権運営の核に「戦後政治の総決算」を掲げ、外交面では時のロナルド・レーガン米大統領を相手に、「ロン」「ヤス」とファーストネームで呼び合うなど親密な関係を築き、冷戦時代の対ソ連(現・ロシア)戦略をにらみながら、「日米は運命共同体」として西側陣営での発言力確保に腐心していた。
一方、内政面では前任の鈴木善幸政権が手をつけた「第二臨調」を活用、日本電電公社、日本専売公社、日本国有鉄道の三公社の分割民営化、あるいは規制緩和を進め、国債の依存度を下げることにも成功している。民間活力を重視、行政改革、財政再建を実現するために、それまでの政権による経済政策を改め、「小さな政府」に舵を切ってもみせた。
こうした裏では、常に各省庁の官僚を巧みに活かし、動かす後藤田の才覚が目立っていた。政権が「官邸主導」で次から次へと仕事をしてしまうため、自民党内では人気がなかったが、こうした機敏な政権運営には国民から大きな支持があった中曽根政権だったのである。
そうした中曽根政権に対する国民の最も大きな拍手は、昭和58(1983)年9月1日に起きた「大韓航空機撃墜事件」への対応であった。事件は、日本時間午前3時29分、ニューヨーク発ソウル行き大韓航空のボーイング747ジャンボ機が、サハリン沖上空でソ連のスホーイ15戦闘機のミサイル攻撃を受け、モネロン島付近に墜落、乗員29人と日本人28人を含む15カ国の乗客240人全員が死亡するというものだった。
日本は、どう対応すべきか。事件には、複雑な要素が多々含まれていた。日本人乗客は直接の当事者ではなく、軍事大国であったソ連を刺激することは北の海での緊張が懸念される一方、当時の防衛庁がつかんでいた情報を明らかにすることは、国の防衛機密をオープンにしてしまうことになる。一つ対応を間違えれば、中曽根内閣は吹っ飛びかねないし、場合によってはソ連との戦争に巻き込まれかねないとの懸念もあった。
結果的には、中曽根首相が圧倒的信頼を置いた後藤田官房長官に対応の全権をゆだね、これが功を奏した形で、あらゆる懸念を回避できたのだった。
★「真剣勝負」が共通の二人
事件対応での後藤田は、警察庁長官、国の「危機管理」のトップとしての実力を存分に発揮した。外務省、防衛庁、内閣調査室を中心に大韓航空機の交信記録をはじめ、あらゆる情報を官邸に上げさせ、後藤田自身が解析、対応を提示した。
結果、当初は知らぬ存ぜぬの対応だったソ連側も、次々と日本側に攻め立てられ、最終的には「民間機だとは認識できなかった」との“弁解入り”ながらも、撃墜の事実だけは全面的に認めざるを得なかったのである。
こうした過程で、後藤田が事にあたった各省庁に命じたことが、一つあった。「日本は大国にあらずという意識で対応せよ」と。これは同時に、時にタカ派としてナショナリズムに傾きかねない「主君」中曽根に対する、「名参謀」としての後藤田の“警告”でもあったのである。
中曽根政権は、こうした後藤田の支えもあって5年の長期をまっとうした。そのさなか、影響力の温存をうかがって中曽根政権誕生に力を貸した田中が倒れ、これをもって中曽根は“独り歩き”を始めたということでもあった。
筆者は、中曽根が90歳を超えて間もない頃、その講演を聴いたことがある。いわく、次のようなものであった。
「私は(首相在任中)国家を背負うにあたって、一番心懸けたのは何事も安易に走らぬことであった。ために、自らを修めることを常に忘れなかったつもりだ」
大勲位・中曽根康弘、101歳の大往生であった。「希代のパフォーマー」「風見鶏」などと揶揄されはしたが、真剣勝負で生きた姿ものぞける。田中角栄もまた、自分の生きる姿勢が同様であったことから、そのあたりに「良質の株だが、上場株ではない」と言いつつも、あえて中曽根政権を誕生させた“根っ子”があったのではと思われる。
(本文中敬称略)
***********************************************
【著者】=早大卒。永田町取材49年のベテラン政治評論家。抜群の政局・選挙分析で定評がある。著書に『愛蔵版 角栄一代』(セブン&アイ出版)、『高度経済成長に挑んだ男たち』(ビジネス社)、『21世紀リーダー候補の真贋』(読売新聞社)など多数。