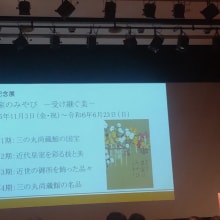幼少時からマンガやドラマ作品で「努力」「忍耐」「根性」を打ち出した、いわゆる“スポ根もの”に親しんできた影響もあるのだろう。これをリング上で再現してみせたのが、プロレスラー・小橋建太である。
高校卒業後にいったんサラリーマンとして就職するも、プロレスラーになるため退職。新弟子試験では書類審査で落選するが、それでも諦めることなく全日本プロレスの事務所へ直談判。通っていたトレーニングジムの会長で、プロレス界に知己の多い遠藤光男の紹介を得て、なんとか全日本プロレスへの入門を果たした。
「実のところ、当時は大相撲十両・玉麒麟(田上明)の入門が決まっていて、20歳すぎで特別な格闘技経験もない小橋は、完全に“いらない子”でした」(プロレスライター)
それでも小橋は、並外れた練習を積み重ねることで徐々に周囲に認められ、ついにメーンイベンターまで上り詰めた。
「ウエイトトレーニングには否定的だったジャイアント馬場が、小橋の練習ぶりに感化されてそれを取り入れたそうです」(同)
一方、佐々木健介も小橋同様、努力と根性でのし上がったプロレスラーである。
長州力に憧れてジャパンプロレス入りしたものの、決して体は大きくなく、格闘歴も目立ったものではなかった。そのため、健介に対する長州の方針は、「適当にしごいて追い出してしまえ」だったが、そんなパワハラ稽古に耐え切ったことで、目をかけられる存在となっていった。
「長州の直弟子として、新日本プロレス入団後は優遇されたように見えましたが、弟子だからこその使い勝手のよさから、重要な試合では損な役回りをさせられることも多かった」(同)
UWFインターナショナルとの対抗戦での垣原賢人戦や、新日初登場時の大仁田厚戦などは、健介にとってきっと不本意なものだったろう。しかし、それにもめげず、与えられた役回りを全力で尽くすことで、トップの一角を担うまでに成長していった。
そんな小橋と健介の初対戦となったのが、2005年7月18日、プロレスリング・ノアの2度目となる東京ドーム大会であった。
いずれもラリアットを得意とするパワーファイターと、スタイルも似た両者。健介オフィス(のちにダイヤモンドリング)を立ち上げたばかりでノア初参戦となる健介と、直前にGHC王座を力皇に明け渡すまで“絶対王者”と称された小橋が、いったいどんな試合を繰り広げるのか。
勝敗への興味は自ずと高まったが、4月のノア武道館大会でカードが発表されて以降、健介は一切、コメントを口にしなかった。
これについて健介は、試合後「コメントを口にしないことで己の緊張感を高めていた」と語っている。それほど特別な試合だったというわけだ。
これは小橋も同様で、入場テーマ曲にはGHC王座戴冠前まで使っていた『グランド・ソード』を選んだ。健介戦での原点回帰を期していたのだ。
6万2000人の大歓声の中、いきなりの健介のバックドロップで始まった試合は、手探りなしの一直線。互いの得意技を惜しげもなく繰り出していく。
山場は、今なお語り継がれる伝説のチョップ合戦。5分以上にもわたって互いに繰り出した逆水平チョップの総数は、なんと218発を数えた。
衝撃から逃れることなく体を前に突き出して、相手のチョップを受け続ける。1発ごとに飛び散る汗のミストが、ライトに照らされてキラキラと輝く。2人の厚い胸筋は、ドームのスタンド席から分かるほど、ドス黒く変色していった。
この試合に影響され、闇雲にパンチやエルボーの打ち合いをするレスラーが増えたが、このときの2人とは1発ごとの重みが違う。チョップだけで試合が終わったとしても、きっと観客は満足する。それだけの迫力は、おいそれと真似できるものではない。
最後はローリング袈裟切りチョップの連発からのラリアットで、小橋が健介を抑え込んだが、もはや勝敗など関係ない。両者の激闘を讃えるファンの大歓声は、いつまでもやむことがなかった。