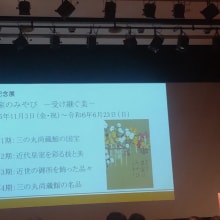当時、多くのファンがそう感じたものだった。
「まともにやったら殺されるんじゃないか」
1980年2月27日、蔵前国技館。ウィリー・ウィリアムスとの『格闘技世界一決定戦』−−。
このころ、ウィリーのバックボーンである極真空手に対するマスイメージは、まさしく「地上最強のカラテ」であった。極真の道場生が街を歩けばチンピラヤクザもこれを避ける。喧嘩や果たし合いとなれば、これに勝る格闘技はない、と。
こうした印象の多くは、梶原一騎原作の劇画『空手バカ一代』によって作り上げられたものではあったが、それ以上に、当の門下生たちが「極真こそが最強」との矜持を持ち、このことが一層、極真幻想を膨らませていた。
ウィリーはそんなツワモノぞろいの極真空手にあって、さらに規格外。クマと素手で戦い、極真世界大会では反則負けも厭わなかった荒くれ者で、身の丈2メートルにも迫る巨躯から繰り出される正拳突きをまともにくらった日には、さすがの猪木といえども無事に済むわけがない…。
「ただ、ウィリーの“熊殺し”とはあくまでも映画の演出で、実際に闘ったのはいわゆるレスリング・ベアという調教されたクマ。そんなウィリーを最初に見た往年の名キックボクサー・藤原敏男の感想は“ライト級の俺でも勝てそう”という辛辣なものでした。これを藤原の師匠である黒崎健時が猛特訓によって鍛え上げた、いわば発展途上の選手だったわけです」(夕刊紙記者)
また極真大会における三瓶啓二戦、襟をつかんでの反則負けも「外国人選手に優勝をさせてはならない」という周囲の圧力からのもので、決してウィリー自身の本意ではなかったといわれている。
だが、同時進行ドキュメントとして週刊少年マガジンに連載されていた、やはり梶原原作の劇画『四角いジャングル』には、もちろんそんな実態は描かれていない。そこに登場するウィリーは、あくまでも極真空手史上最高のバケモノじみた実力者であり、人心を持たない野獣であった。
そうして極真の看板を背負ったウィリーがリングに立つことで、試合は極度の緊張感を帯びたものとなっていった。
ウィリーの師匠である大山茂は「ウィリーが負ければリング上で腹を切る」と、その覚悟を語る(劇画内のことではあったが)。
当日セコンドに就いた極真勢は「いつでも代わりにリングに上がる」とばかり、実際に闘うウィリー以上の闘気をみなぎらせ、その空気はブラウン管越しにもひしひしと伝わってきた。
「ただ、今あらためて試合の映像を見ると、ウィリーの繰り出す上段蹴りはモーションが大きくて、とても猪木を捉えられそうにない。鋭く放たれる正拳突きや膝蹴り、肘撃ちも、急所を狙っているようには見えません」(格闘技ライター)
後には、この試合の実質的なプロモーターでもあった梶原自身も「あれは八百長だった」と暴露している。
2ラウンドでの両者リングアウトから立会人・梶原の裁定で試合続行、そして4ラウンド両者負傷によるドクターストップまで、全てが梶原の筆による筋書き通りだった、と。
しかし、それが真実だったとしても、だからといってこの試合に価値がないかといえば、決してそんなことはない。
「絶対に負けられない闘い」として臨んだ極真勢の意気込みは紛れのない本物で、そこから生まれた緊張度MAXの空気感は、いかなるプロ格闘技興行においても味わえないだけのものが確かにあった。
ウィリーの蹴りに「かすっただけでもKO必至」と固唾をのみ、懸命の防戦から寝技で攻勢に回る猪木に快哉を送る−−。そんな、一時たりとも目を離せない緊張感に満ちていたことに間違いはない。
梶原劇画による事前プロモーションから始まり、周囲までをも本気にさせた舞台設定、そしてもちろん、ピリピリと張り詰めた試合を実現させた猪木とウィリーの両者まで全てがかみ合った、最高の名勝負の一つであった。